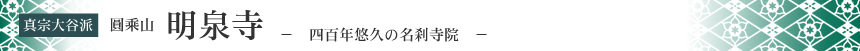- 連載トップページ>
- 劫火の中になお生命ありて その5
「劫火の中になお生命ありて」
円乗山明泉寺14世住職:水谷光子
劫火の中になお生命ありて その5
戦災から早くも五十年以上経っている。私にとって、それまでの人生の三倍の歳月が流れ去った。それでも、こうして文章にしていると、漸く癒えかかった肉体の傷口を、自らのメスで再び切開していくような痛みが走る。『戦争体験を風化させるな』と言われるが、記録の意義は承知しつつも、ペンを持てない人々は、今なお決して少なくないだろう。 妹は、その後二か月の入院生活で、奇跡的に生命を取り止め、現在は夫にも子にも孫にも恵まれ、幸せに暮らしている。私も夫を迎え寺を継ぎ、仕事もしてきたし、お陰で念願の本堂・会館・庫裡とあい次いで再建も叶えられ、坊守として更に住職として、母の生命を生き継いでいる。罹災直後から、戦後の混乱期の体験にも触れたいが、いずれ別の機会に・・・。病院では、生きながら患者の膿に湧く蛆虫を、ピンセットで摘み取るという、実に原始的な蠅との戦いも体験している。食糧難も辛かったが、その飢餓感よりも、それに伴う人の心の荒廃ぶりを、見ることの方が更に切なかった。鏡に映したら、私もまた似たり寄ったりで、それ程変わらぬだろうし、また汚れねば生きていけない現実の苛酷さもあった。ともあれ、今回は劫火の一夜に焦点を絞っておく。
罹災の日までの私は、静岡市女子国民学校に(現・末広中学校)助教諭として奉職。私より三・四歳若い女生徒達六十人を受け持っていた。学級数・二十七学級。職員は三十六人。その内男性は、校長・事務職を含めて僅か七人だったと思う。事務職は元校長で、定年後の方だった。青壮年男性は、あらかた戦場に赴き、どこの職場もほとんどが女性と老年の男性だったように思う。授業時間は週三十四時間。ブランクは全く無し。休暇は元より、病気でも風邪位では、欠勤の出来ない状態だった。更に毎日二時間ほどは、作業を割り当てられた。さつま芋の畝作りと、防火用の貯水池を掘る作業だった。どちらも固い校庭を掘り起こす重労働だが、生徒たちは馴れぬ鍬を手に、よく頑張ってくれて、つくづく感心させられたものだった。警報が発令されると、生徒を直ちに帰宅させ、職員はご真影と校舎の警備に当たるのである。当番制ながら、夜間でも発令されると出勤するわけで、解除の時刻によっては、その儘学校で仮眠し、引き続き翌日の勤務に就いていた。職業柄、緊急時に備えて、救急法や看護法も勉強させて戴いたし、人工呼吸の実技も、一応習得していた。防空服装も研究して、手製で整え身に着けていた。劫火の中を生き抜けた原因として、こんなことも役立っていたとは思う。また年齢的にも生命力の最も旺盛な時期ではあった。しかしそれだけだったか。私自身の力のみで生き抜いたとは、どうしても思えない。『生かされるべくして、生かされた生命』という思いが強いのである。
幸いにして生き延び、どなたの目からも正常に見られている私だが、実は未だに後遺症に悩まされているのだ。私は今でも、地下道を歩くことに抵抗を覚える。頭の上を電車やトラックが通ることに、大袈裟に言えば、生命の恐怖を感じるのだ。夜空を彩る花火にも、遠くからでさえ、美しいと眺める心のゆとりはない。まして近くに行き、群衆に混じって、真下から眺める気には、とてもなれない。飛行機の爆音を聞けば、必ず位置を確認し、若し墜落すれば・・・と、その位置を想定して身を避けてしまう。戦後の木造バラックの時代は、二階でガタガタ騒がれると、その下では落ち着けなかった。理屈では総て諒解している。そんな私の杞憂を、もう一人の私に、滑稽だと嘲笑させるのだが、それでも本能的に行動してしまう。明らかに私は精神を病んでいる。空襲の劫火の一夜を体験したことによる後遺症である。しかし、私を知るどなたからも、狂人扱いされたこともないし、精神科医師の診察を勧められたことすらない。十分に自省し、病身の私を、健康なもう一人の私が、精一杯コントロールしてきたから、気付かれなかったに過ぎない。年月を経るに従って、幸いに病気は次第に軽くなってきた。しかし、本当に全快する日が来るか否か、私にも判らない。戦後も教職にあったし、ひたすら自重を重ねて生きて来た歳月なのである。人間は極限状況に追い詰められると、性格まで歪むと聞くが、それは真実である。正常に見られている私にして、斯様な状態である。あの当時様々な衝撃を受けて狂った人が、大勢目に付いたが、私のように、潜在的に精神を病んだ人を含めたら、その何十倍になるだろう。実に数え切れない筈である。