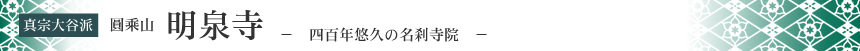- 連載トップページ>
- 劫火の中になお生命ありて その2
「劫火の中になお生命ありて」
円乗山明泉寺14世住職:水谷光子
劫火の中になお生命ありて その2
境内を抜け、本堂の後ろ側の幅七尺程の路を通って、墓地へ辿り着いたら、裏の道路には、更にひどい火の手が上がっていた。両側の建物の煙と炎で、幅三間ほどの道は全く見えず、とても前には進めない。異常な風が起きていて右から左から、炎が掃かれるように道に流れ、道を隠してしまう。まさに進退窮まったのである。その時、坪庭の塀を乗り越して、祖父を背負った母が現れた。とにかく家族六人全員が、顔を揃えられたのである。再び表の道に引き返すしかないと判断したその時、本堂にまで火の手が上がった。飛行機の爆音・爆弾や焼夷弾の炸裂する音・建物がパチパチ燃える音・崩れ落ちる音・・・。それらが入り混じって、本堂にいつ何発落とされたか、全く気が付かず、火が上がって初めてそれと知るのであった。
そこへ、やはり逃げ遅れた隣のご主人が現れ、勧めてくださったので、私達は塀をよじ登り、隣の風呂場で、交替に水風呂に浸った。勿論、衣服も防空頭巾も着けたままである。綿入れの頭巾も、モンペや服も、手編みの分厚い手袋や靴下も、お陰でたっぷり水を含み、このことによって、私の生命は守られたとも思われる。その間にも、煙はいよいよ濃くなり、火は勢いを増すばかり・・・。百坪足らずの墓地の北東側は、幅三間程の道路だが、他の三方は、殆ど地所一ぱいに、庫裡や隣家が建っている。平屋か二階建てであるが、総て木造である。五年前に、静岡大火を経験しているが、とてもその比ではない。延焼か飛び火か、それとも別の焼夷弾によるのか。ともあれ、次々に火を噴き始めていた。どす黒い煙は更に濃くなり、痛くて目を開けてはいられない。たっぷり水を含ませたタオルで、鼻と口を覆っていたが、次第に乾き、喉が痛み、声も出せない。呼吸も苦しい。深く吸っても浅く吸っても、苦しさは変わらない。だったら、出来るだけ浅く吸って、少しでも肺を守るべきか・・・などと試行錯誤。煙はいよいよ濃くなり、もう三寸先も見えなくなった。こんな状況の中で、私達七人は、いつとはなく離ればなれになっていた。各自が、さして広くない墓地の中を、逃げ惑っていた筈である。
墓地の通路は舗装してあるので、焼け石となり、余熱で熱い。石塔は真っ赤に染まり、さながら鍛冶屋で見る焼入のように、透きとおってきた。墓地の南東側が一部、空き地になっていて、まだ舗装されていない。そこまで辿り着いたら、足の裏が少し和んだ。冷んやりとまではいかないが、とにかく土の感触は、例えようもなく快い。しかし此処にも、長くは留まれなかった。隣接の建物が激しく燃え始めてきたからである。煙も火も上に向かうので、姿勢を低くすると、呼吸が幾らか楽になることに気付く。また周囲の建物の燃え方によって、風の方向も速さも、絶えず変わっている。その辺の状況を見極めて、沈着冷静に行動しなければならない。
後頭部が熱いので手を当てたら、防空頭巾は水に漬けてあったのに、既に乾ききり、綿と共に後ろ髪が燃えているのだった。体全体がまさに焦熱地獄の真っ直中にあるので、髪がかなり燃えているのに、気付かなかったのである。見ればモンペの膝も上着の袖も焦げて、大きな穴が幾つもあいていることが、手触りで判る。それからは、両手で体のあちこちを絶えず叩くように気を配る。降りかかる火の粉を払い落とし、叩き消すのである。そのうちに、道路を隔てた三階建てのビルの窓からも火を噴き始めていた。コンクリートの建物だから、燃える筈はないが、中の商品に火が付いたのだろう。建物が爆発するかも知れない。石塔のような状態になって、コンクリートの塊が飛び散ることも考えられる。漸く落ち着きかけていた心が激しく怯む。
『もうこれまでかも知れない』覚悟は出来ていた。今生最期の勤行と、正信偈が口をついて出てくる。誦経しつつも、体は火から懸命に逃げているのだった。『今生に生を享けて、既に十八年余。お蔭で幸せな人生を歩ませて戴いた。まだまだ生きたいし、やりたいことは一杯残っている。でもこれが私のさだめかも知れない。いよいよ彼の国に迎えられる時が来たようだ』けれども、百二十句(八百四十字)の偈文をあげ終わっても、私はまだ生きていた。来し方十八年の生活のさまざまな場面が、次々に脳裡に現れては消えていく。静岡幼稚園・付属小学校・精華高等女学校・延身隊員としての三光航空会社・そして現在勤めている女子校(現末広中学)の生活。諸先生・担任している六十人の生徒の顔・顔・顔・・・。この期になって何故、急に浮かんでくるのか。一人ずつ大写しになっては遠ざかり、次々に顕れては消えていく。何故だったのか、今もその意味を求め続けているのだが・・・。墓地の北隅に、我が家の墓がある。五年前に亡くなった祖母(真)も、一年前に亡くなった妹(俊子)も、生後間もなく亡くなった妹(恵子)弟(清)も、皆ここに眠っている。最後の場所は、我が家の墓前で・・・と、急に思い付いた。幸いにその時、火の勢いはその方向が一番弱まっていた。相変わらずの濃い煙の中で、石塔に触れぬように気をつけながら、這うようにして何分もかけて漸く辿り着いた。祖母に甘えたかったのだろうか。墓前についてからは、ひたすら念仏を称えるだけだった。安心したせいか、突然猛烈な睡魔に襲われた。『一酸化炭素にやられたな』と承知しながら、私の意識はみるみる薄れていった。