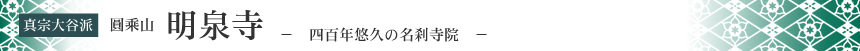- 連載トップページ>
- 劫火の中になお生命ありて その3
「劫火の中になお生命ありて」
円乗山明泉寺14世住職:水谷光子
劫火の中になお生命ありて その3
三十分も眠っていたのか。頭巾を通して再び髪が燃え始めて、漸く目が覚めた。西側の火の手が少し弱くなっていた。『そうだ。建物が燃え尽きたら、火は消える筈だ。消さなくても消える時がくるのだ。自然に消えるその時を待てばよいのだ』私は大発見でもした気分に浸った。こんな簡単なことも判らぬ程に、動顛し続けていたのだった。鉄筋のビルも、窓からの火は少し弱まり、建物そのものは、破壊されてはいないようだった。周囲の建物の火災もそれぞれ峠を越したようだ。『生き延びられるかも知れない』と一人頷き、急に希望と元気が身に満ちみちてきた。頭も少し冴えてきた。けれども、全身綿のようにくたくたに疲れているし、体の節々が激しく痛む。よく考え、冷静沈着に判断して、体力を無駄に使わないことだ。墓地の中央当たりが、大分凌ぎよくなっている。墓石の色でそれと判る。暫くはここにいよう。火の勢いは、辺り一面次第に弱まり、何よりも呼吸が楽になった。『助かったのだ・・・』とはっきり意識した。そして安心して、再び深い眠りに入っていった。
道路を歩く兵隊さんの靴音に目覚めた時は、夜が白々と明け始めていた。四時を少し過ぎていただろう。石塔にまだぬくもりは残っていたが、熱くはなく色も常の色に戻っていた。空も煙や燻りは残っていて、昨日までとは違ったが、それでもとにかく、狂乱の一夜は完全に終わっていたのである。この夜明けの空への感動も、私にとって生涯忘れ得ぬものとなった。
すぐ近くに妹が眠っていた。意識もすぐに戻った。ひどい焼傷を負っているが、とにかく生きていてくれた。東側の角近くで、祖父が亡くなっていた。衣服も殆ど焼け、体の一部は骨が出ているという程の、実に無惨な焼死体であったが、端然と坐り合掌したまま、少しも姿勢が崩れていなかった。『何と素晴らしい信念・素晴らしい往生であろう』私は今もあの時の感動が蘇ってくるのを覚える。身動きの侭ならぬ祖父は、『逃げたくとも逃げられず』というより、『逃げる気』を全く持つことなく、その場所から動かなかったのであろう。幼くして明泉寺の養子となり、荒廃した寺を守り、漸く建立できた本堂が、三十余年で劫火を浴びたのである。断腸の思いで本堂の焼け落ちるのを見届けながら、自らも息絶えたのであった。父はその隣で、塀に寄りかかって倒れていた。昏々と眠っていて、揺り起こしても目覚めない。着ていた国民服は、それ程焼けてはいない。途切れがちながら、脈は微かにある。吸う息はよく判らないが、吐く息はそれと判る。弱視と心臓弁膜症の体で、一晩を精一杯頑張り抜いた果ての姿であった。頭を打ったのであろう。血が滲んでいる。『どうして助けたらよいか』・・・。
人の気配を感じて、焼け落ちた木戸口から裏の道に出て、兵隊さんに助けを求めた。この時は未だ、要所々々に非常線が張られ、外部からは一般の人が立ち入りできない状態だったそうだ。「どこから入って来たの」「ずっとここにいました」服装は焼け焦げ、髪は振り乱れている私の姿に、魂消た兵隊さんは、あの劫火の中に閉じ込められて、しかも生き延びている私の存在を、とても信じられないようだった。あれこれ聞くが今の私は、ゆっくり話してはいられない。一刻も早く父を救助して欲しい。せき立てて、父を担架で病院に運んで貰うと共に、妹の救助も頼んだ。暫くして、別の兵隊さんが迎えに来て、妹は田町小学校の臨時救護所に担架で運ばれた。祖父の遺体に心を残しながらも、私は妹に付いて行った。その時は、瀕死の妹から離れられなかったのである。当然いる筈と思っていた父は、そこにはいなかった。父の安否と居場所を気遣いながら、どうにもならぬ私自身が、無性に歯痒かったのだが・・・。