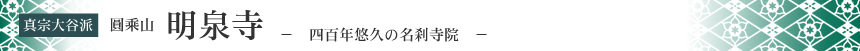- 連載トップページ>
- 劫火の中になお生命ありて その1
「劫火の中になお生命ありて」
円乗山明泉寺14世住職:水谷光子
劫火の中になお生命ありて その1
静岡市が空襲を受けた日、昭和二十年・六月二十日・午前一時頃、私(十八歳)は、母・千佐(三十九歳)、妹・喜久代(十五歳)、弟・威(十二歳)と共に、自宅の防空壕に退避していた。空襲警報は連夜のことで、慣れぎみになっていたが、それにしても、今夜はなかなか解除にならない。その時、父・壽(五十歳)は、阿弥陀様をお迎えに本堂へ行っていた。間もなく、お台座から外し、七条のお袈裟をお着せし、お抱きして戻って来たのだが、その父を待つ間の長かったこと。不安だったこと・・・。
もう一つの気掛かりは、祖父・了故(七十九歳)であった。この時、祖父は奥座敷の布団の中だった。老衰に加えて、リウマチで関節を痛めているため、いつも壕に入ることを拒むのであった。親戚や知人からの疎開の招きにも、感謝はしながらも、固く辞退するばかりだった。多分、遠からざる死を覚悟の上で、どうしても、寺から離れられなかったのであろう。廃佛棄釋の時代にあって、荒廃した明泉寺を引き受け、坊守・真(昭和十四年・六十八歳で逝去)と共に、必死で寺を守り、檀信徒の皆様のお力を得て、あの立派な本堂を再建できたのは、祖父の四十代後半の筈である。勿論、家族の足手まといになるつもりなどは全く無く、時が来たら、自室で静かに最期を迎えるつもりだったのであろう。私も年を重ねた今、祖父のそんな気持ちが、切ない程によく判るが、当時は、『家族の身にもなって欲しいのに・・・』という思いがあった。しかし、決して誰も口には出さなかった。目上に対する当然の遠慮であり、そういう時代だったのである。
父が戻ってから暫く経った。辺りのざわめきもいつしか鎮まり、何となく不気味な気配だった。今にして思えば、先のざわめきは、近所の方たちが家を捨てて、安倍川方向などに逃げていく騒音だったようである。弟の主張で壕の入り口をそっと開け、外に出てみたらさあ大変。表の道路の向こう側に、火の手が上がっているではないか。茫然として一瞬立ちすくんだが、その間にも、火はこちらへ燃え拡がってくる。もうこうしてはいられない。父の意見で、墓地を通り抜け、裏の道路から逃げることにした。母は祖父をお迎えに奥座敷へ走った。
我が家の防空壕は庭の一隅で、本堂からも庫裡からも、かなり離れた場所にあり、金木犀の大木や梛・椿・山茶花などの植え込みに隠れ、上空からは全くそれと判らぬように作ってあった。排水もよく考えてあったし、壁替わりとして土止めに畳を使うなど、当時としてはかなりよく出来ていた。勿論、父が考えに考えて、職人に作らせたものであった。この壕一つにも、父の生きる姿勢がよく表れている。結果的には、壕に頼り過ぎて逃げる機会を失なったのであるが、父としては、真に止むをえぬ事情であったと思う。一つには祖父である。祖父を置き去りにして、逃げ出せる筈がない。連れ出すとしても、本人が状況の理解もできず承知もしない。そして無理に動かしても痛みに耐えられないだろう。二つには、父の体力である。心臓弁膜症が進んでいて、人並みに走られる状態ではなかったし、視力も衰えていて、当時は新聞の記事は全く読めず、見出しが読めたり読めなかったりの状態だった。明暗はよく判り、家の中の生活に困らない程度ではあったが、外出には母などの付き添いが必要だったのである。三つにはご本尊様のことである。他のお掛軸などは疎開したが、阿弥陀様だけは、父が自分の命に懸けて、お給仕するつもりで、疎開は全く考えなかったようだった。そのことも、逃げる機会を失った原因だったとは思う。それにしても、静岡市の空襲は、殆ど初めてのようなもので、新聞に報道されない程度の空襲はあったが、一般には知らされず、父も知らなかったようであった。その頃は、新聞・ラジオなどの報道は極度に規制され、戦局のニュースなど、軍にとって都合の悪い事は皆伏せられ、国民はかなり不安を感じつつも、口にさえ出せない時代だったから、父の時局の認識が、少し甘かったかも知れないが、仕方ないことと思う。ともあれ『阿弥陀様は、窒息の心配がないから、壕の中の方が安全だろう』と、父は判断した。私達にも各自の貴重品は残させて、壕の入り口を完全に閉ざし、全員身一つで跳び出したのであった。